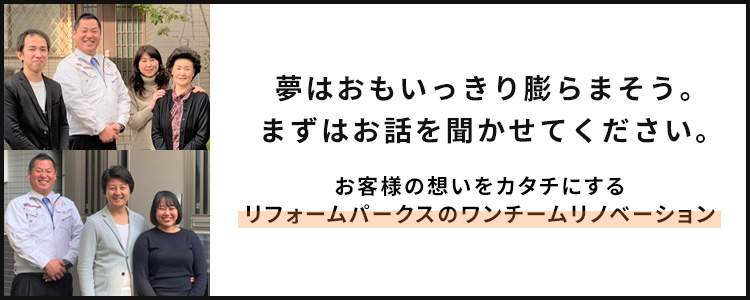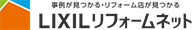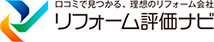2022年9月
完全分離型の二世帯住宅の後悔例について解説します
投稿日:
カテゴリー:リフォームのお悩みあれこれ
「トラブルなく過ごすために意識すべきことを教えてほしい」
このようにお考えの方も多くいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、完全分離型の二世帯住宅における後悔例と後悔しないために意識するべきことをご紹介します。
ぜひ最後までご覧ください。

□完全分離型の二世帯住宅における後悔例
完全分離型の二世帯住宅にするか悩まれている方も多いでしょう。
では、完全分離型の二世帯住宅ではどのような後悔の声があるのでしょうか。
ここでは、完全分離型の二世帯住宅の後悔例をご紹介します。
1つ目は、生活音に気を遣うことです。
完全分離型でも、生活音が気になったり、気を遣ったりします。
生活スタイルがどうしても異なりますので、活動時間の違いによって生じる騒音に悩むことが多いそうです。
2つ目は、家に友人を呼びにくくなったことです。
完全分離型だとしてもなかなか呼びにくいことがあるようです。
3つ目は、光熱費の支払いでトラブルになることです。
二世帯住宅であれば、光熱費の支払いは一括で請求されますので、その支払いにおいて後々トラブルになることもあるようです。
4つ目は、外回りの掃除や手入れでトラブルになることです。
完全分離型の家でも、庭やバルコニーは共用です。
手入れの分担を決めておかず、後々トラブルになることもあるようです。

□完全分離型の二世帯住宅で後悔しないためには
ここまでで、よくある後悔についてご理解していただけたと思います。
できれば、トラブルなく安心して暮らしたいですよね。
では、後悔しないためにどのようなことを意識するべきでしょうか。
まず、生活音が気にならない工夫をすることです。
防音性能を上げたり、間取りを工夫するなどして、生活スタイルが異なっても騒音に繋がらないような工夫をしてみましょう。
次に、お互いの要望を事前に伝えることです。
事前に意見を伝えておくことで、トラブルを防ぎましょう。
最後に、生活ルールを決めておくことです。
光熱費や掃除の分担等のルールを決めておくと安心です。
以上を意識して、トラブルを防ぎましょう。
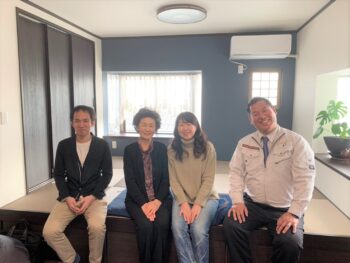
□まとめ
今回は、完全分離型の二世帯住宅における後悔例と後悔しないために意識するべきことをご紹介しました。
後々のトラブルを防ぐためにも、この記事でご紹介したことを意識しておきましょう。
何かご質問や疑問点等がございましたらお気軽にお問合せください。
この記事がお役に立てば幸いです。
ここまでブログをご覧いただきありがとうございます。
お悩みの解決にお役立ちできていれば幸いです。
リフォーム・リノベーションの主役はあくまで、お客様ご自身です。
もし今、お客様のやりたいリフォーム、
実現したいリノベーションのカタチが
明確になっているのであれば代表の菊井にお聞かせください。
LINEからご相談のお客様は
リフォームパークスLINE公式アカウントへご登録頂き、お声がけください。
二世帯住宅へのリフォームをご検討中の方へ!間取りの考え方をご紹介!
投稿日:
カテゴリー:リフォームのお悩みあれこれ
そこで、今回は二世帯住宅の間取りを考えるポイントと二世帯住宅のタイプをご紹介します。
おすすめの間取りについてもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

□二世帯住宅の間取りを考えるポイントとは?
二世帯住宅の間取りを考える際、どのように考えれば良いのでしょうか。
よくわからない方も多いでしょう。
そこでここからは、リフォームして二世帯住宅にする際の間取りの考え方のポイントをご紹介します。
1つ目は、一緒に食事をするかどうかです。
それにより、リビングやダイニングを一緒にするかどうかを決められるでしょう。
2つ目は、キッチンを共有にするかどうかです。
一緒に使ってもいいのか、それとも別々で使いたいのかによっても変わるので話し合いましょう。
3つ目は、浴室やトイレを共用にするかどうかです。
共有にすることで、水道や光熱費を節約できるというメリットがありますが、混雑するという懸念点もあります。
4つ目は、玄関や廊下を共有にするかどうかです。
玄関を一緒にするか別々にするかは、間取りを大きく左右するのでじっくりと検討しましょう。
以上が二世帯住宅の間取りを考えるポイントでした。
ぜひ覚えておいてください。

□二世帯住宅のタイプについて
二世帯住宅にはどのようなタイプがあるのでしょうか。
ここでは2つのタイプをご紹介します。
*完全分離型
まず、完全分離型です。
親世帯と子世帯が完全に分離しているタイプです。
この場合、将来的に子世帯が独立した場合や、親世帯が亡くなられた場合に、そのスペースを賃貸に出すなど有効活用できるようにすると良いでしょう。
*部分共有型
次に、部分共有型です。
このタイプの場合、両世帯の交流と個人のプライバシーを確保することが重要です。
例えば、1階に両世帯で食事を楽しめる大きなリビングを取り入れ、2階に子世帯が気兼ねなく使えるリビングを別に設けることはどうでしょう。
プライバシーを確保しつつ、交流が途切れない間取りにできるでしょう。

□まとめ

今回は二世帯住宅の間取りを考えるポイントと二世帯住宅のタイプをご紹介しました。
間取りを考える際は、具体的な生活をイメージして、何を共有するかをじっくりと話し合って検討しましょう。
二世帯住宅へのリフォームをご検討中の方は、ぜひ当社にお任せください。
全力でサポートさせていただきます。
ここまでブログをご覧いただきありがとうございます。
お悩みの解決にお役立ちできていれば幸いです。
リフォーム・リノベーションの主役はあくまで、お客様ご自身です。
もし今、お客様のやりたいリフォーム、
実現したいリノベーションのカタチが
明確になっているのであれば代表の菊井にお聞かせください。
LINEからご相談のお客様は
リフォームパークスLINE公式アカウントへご登録頂き、お声がけください。
介護用ベッドを使用する際の部屋の広さについてご紹介します!
投稿日:
カテゴリー:リフォームのお悩みあれこれ
介護用ベッドを使用するとなったら、どれくらいの広さにすれば良いかよくわかりませんよね。
この記事では、介護用ベッドを使用する際の部屋の広さと心地良く過ごせる部屋にするための工夫をご紹介します。
ぜひ最後までご覧ください。

□介護用ベッドを使用する際の部屋の広さとは?
介護用ベッドを使用されている方も多いでしょう。
では、介護用ベッドを使用するのであれば、部屋はどれくらいの確保をすれば良いのでしょうか。
使用者の体の状態に分けてご紹介します。
*移動手段が独歩や杖の場合
この場合であれば、ベッドの起き上がる方のスペースはそこまでいらないでしょう。
ベッドを壁や窓に寄せれば、四畳半でも可能でしょう。
*移動手段がスタンダード型の車椅子の場合
車椅子での動作となるので、部屋の入り口からベッドまでの動線を確保しなければなりません。
ベッドと車椅子を乗り移るためにも、1メートル程度の幅を確保する必要があります。
そのため、四畳半ですと少し狭いかもしれません。
*移動手段がリクライニング型の車椅子の場合
起き上がりがなかなか厳しい場合、リクライニング型の車椅子を使用される方もいらっしゃると思います。
この場合、さらに大きな車椅子となりますので、さらに広いスペースを確保する必要があるでしょう。
具体的には、六畳程度、かつ入り口が90センチメートルほどの幅が良いでしょう。

□心地良く過ごせる部屋にするための工夫について
ここまでで、どれほどのスペースを確保するべきかご理解していただけたと思います。
そこで、ここからは心地良く過ごせる部屋にするための工夫についてご紹介します。
1つ目は、照明です。
ご高齢の場合、20歳代より2〜3倍の高い照度が必要と言われています。
そのため、若年者の1.5倍ほどの明るさにすることをおすすめします。
2つ目は、温度・湿度です。
ヒートショックを起こさないようにするためにも、温度は22〜24℃、湿度は60パーセントに保つと良いでしょう。
3つ目は、換気をすることです。
空気がこもらないように、こまめに換気をしましょう。

□まとめ
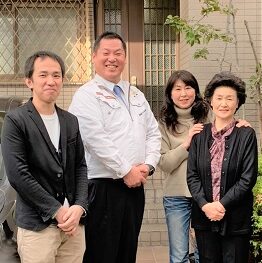
今回は、介護用ベッドを使用する際の部屋の広さと心地良く過ごせる部屋にするための工夫をご紹介しました。
介護用ベッドを使用される方の体の状態によっても広さは異なりますので、その方の状態と向き合って検討することをおすすめします。
ここまでブログをご覧いただきありがとうございます。
お悩みの解決にお役立ちできていれば幸いです。
リフォーム・リノベーションの主役はあくまで、お客様ご自身です。
もし今、お客様のやりたいリフォーム、
実現したいリノベーションのカタチが
明確になっているのであれば代表の菊井にお聞かせください。
LINEからご相談のお客様は
リフォームパークスLINE公式アカウントへご登録頂き、お声がけください。
最新の投稿
カテゴリー
月別アーカイブ
お問い合わせ
まずはお話を聞かせてください。
私たちはお客様とお話しする工程を
一番大切にしております。